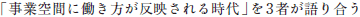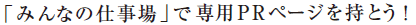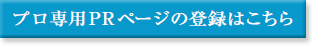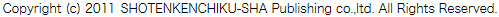- 高松 聡
- ground代表、クリエイティブディレクター
- 西村佳哲
- リビングワールド代表、プランニングディレクター、働き方研究家
- 宮本英治
- ASKUL みんなの仕事場 事業推進 事業部長
オフィスをはじめ、店舗、医療施設、教育施設などさまざまな空間を運営する人々と、それらの空間を設計するスキルを持つ人々。そうした人々の出会いの場を提供するサイトが、アスクル株式会社の運営する「みんなの仕事場」だ。その背景には、近年の働き方の変化、そしてそれに伴う働く空間の変化がある。「仕事場」「空間デザイン」「ブランディング」をテーマに、三人が語り合った。
- 宮本
- 今日は六本木にあるgroundさんのオフィスにお邪魔していますが、いいオフィスですね。
- 高松
- 私たちgroundは十数人の会社です。このオフィスは2010年に開設しました。この2階フロアと同面積の地下フロアという2つの空間を使っています。うちの事務所は、私を含め長時間労働が恒常化しています。起きている時間は全て仕事をしている。そんな人間の集団です。だから2階はオフィスというよりハウスに近いイメージにしました。執務スペースよりも、ソファやキッチンといったリラックススペースの方が大きい。反対に地下フロアは窓がなく、一日中明るさが変わらないので、時間を忘れて仕事に集中できます。ハウス的な快適性とファクトリー的な効率性、この両者を行き来できる環境を、と考えました。
- 宮本
- 私たちアスクルも先日、引っ越しまして、新オフィスには企業理念の「お客様の声を聞き、よりスピーディーに対応する」を反映しています。空間にモニターを設置してお客様からの声をグラフィックで表示する映像演出の仕掛けも備える予定です。1200人の社員が2100坪くらいの広さの中で働いています。

- 西村
- 確かに、どんな空間で働くかは重要ですね。僕が大手建設会社でオフィスプランニングに携わっていたときに分かったのは、「人は働いている環境にとても影響される」という事実です。例えば、グリーティングボードがどこにあるかでコミュニケーションの仕方が変わる。でも、実は見えない環境の方が大きくて、それはOSみたいなもの、つまり「働き方」ですね。オフィスは人と人が働いている場所なので、空間が個人に与える影響の前に、お互いに与え合う影響もある。それをオフィスのデザインでサポートできると思います。例えば、会議室やトイレに行くとき、他のフロアの打ち合わせの様子が見える。誰が何をしているのか、誰がどんな様子か、お互いのアビリティーを可視化してくれるのは空間でないとできないことなんです。
- 宮本
- 仕事場が働き方を決めるとともに、その逆もあるということですね。ちなみにこちらのオフィスを設計された設計者さんは、以前からお知り合いだったのですか?
- 高松
- いえ、色々な人に推薦を聞いて候補に挙がった方です。その後、彼の作品を随分と見ました。図書館へ行ったりして、丸3日間オフィスに関するあらゆる情報を徹底して集めました。ただ、自分が納得いくまで資料を探すにはそれなりに労力がかかるので、簡便に資料収集できるインフラがあれば便利ですね。

- 宮本
- オフィス、店舗、医療、教育施設などの空間をつくりたいという人と設計者や建築家を結びつけるために「みんなの仕事場」を運営しているのですが、特に国内でオフィスをいくつも見ていると、ここ数年、急激に変化しているのを感じます。我々のサイトは「日本中の仕事場を快適にして、そこで働く人を元気にしたい」という理念に基づいた活動です。働く人も、仕事をする空間も変わってきた。そのことを建築家やデザイナーの活動を通じて明確に伝えていきたいと考えています。
- 西村
- このようなサイトが海外であるのは知っていたけれど、今回、国内でこんなサイトがあるのかと少し驚きました。
- 高松
- このサイトに掲載されているオフィスを見ると、経営者自身の感覚も若く、集まる社員の平均年齢も若い企業が目立ちますね。そして、彼らが提供している商品やサービスも、IT関連など新しいものですね。そんな彼らにとって、仕事場そのものが「うちはこういう環境でものづくりをしているんだ」とアピールする一つのブランディング機能を担っている。更に、「どういう風に自分が働けるのか」に意識的な若い人が増えているから、いい人材を採用したい成長企業が今、オフィス環境づくりに力を入れているのではないでしょうか。
- 西村
- ウェブでオフィス空間を見て、「どこの会社に入ろうかな」というようにも機能するだろうと思います。
- 宮本
- そうですね、実際にリクルートで利用されるケースもあるようですが、我々が目指しているのは仕事場環境の価値向上に腐心されている空間を創りたい人にとっての情報源になることです。みんなの仕事場では、より多くのプロの方の情報を提供したいという想いから、プロの方に無料で専用PRページを提供しています。専用ページでは事業概要・作品などを自由に編集・掲載いただけるのが特徴です。そうしたプロの方の情報をもとに創りたい人が自分の想いを実現してくれそうなベストパートナーを探すことができます。まさに、人と人とのコミュニケーションの出発点、プロの方とのファーストコンタクトのきっかけになればいいと思っています。あくまで、最初に出会う「場」を提供できればという考え方です。

- 高松
- 伝統的な終身雇用、年功序列の制度を取らない企業は、報酬システム、オフィスの在り方、服装など、あらゆる面で総合的に働き方のスタイルを提案しています。だから、素敵な働き方をできる多様なオフィスが出てくるということは、日本流の経営や雇用形態、ワークライフバランスなどが変わっていこうとしていることの現れなのではないかと感じています。
- 宮本
- 私がこのサイトでの取材を通じて見てきた企業や店舗、医療、教育施設で働いている方々は、「働くことを楽しんでいるな」と思えました。だから、サイトも働いている方々の顔が見えるような編集をしています。私たちが目指している快適な空間であったり、元気に働ける職場であったり、そうした環境に賛同されるプロの方に「みんなの仕事場」に入っていただきたいという思いがあります。個人事務所の方から従業員の多い企業まで「みんなの仕事場」を通して世の中に自分達の作品を自由にPRしたり、情報を発信できるオープンでフラットな場としてプロの方のお役に立てれば嬉しく思います。
今回の座談会からも、創りたい人(依頼側)の意識が大きく変わってきていることが感じられる。これからはそのような人々に対して、プロの方がどんどん積極的に情報提供・PRしていく必要がある。そんな時代変化の中で、「みんなの仕事場」は創り手にスポットライトを当てることで、これまで空間創りに興味を持たなかった人々に空間創りの重要性や楽しさを伝えていくサイトだ。なお、「みんなの仕事場」は2011年8月末にリニューアルされ、プロの方向けに専用のPRページを無料で提供する。2011年12月には、空間を創りたい人がオンライン上でプロの方を探して依頼出来るマッチングサービスも展開予定だ。

- 「みんなの仕事場」トップページ。現在NHK「サラリーマンNEO」とのコラボレーション企画展開中

- 「みんなの仕事場」では最新の空間事例を数多く見ることができる

- デザイン会社の専用PRページでは、登録したデザイン会社が自社のプロフィールや作品を掲載することができる